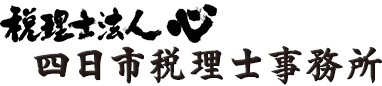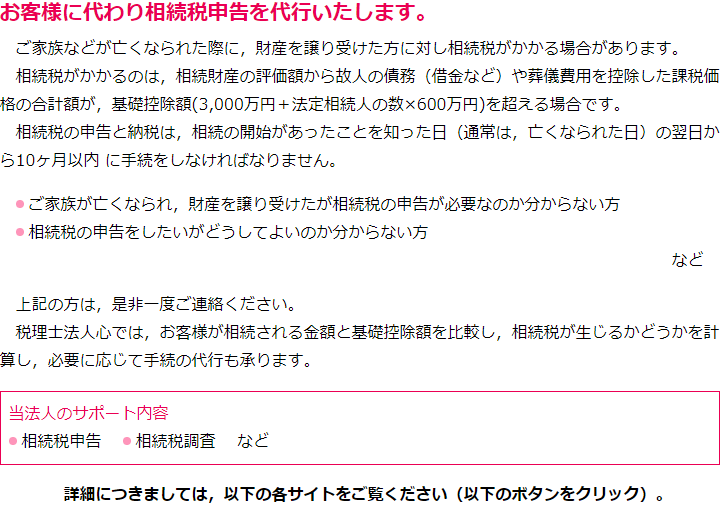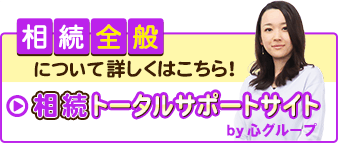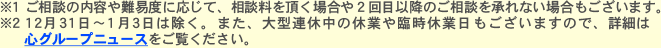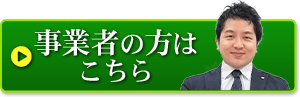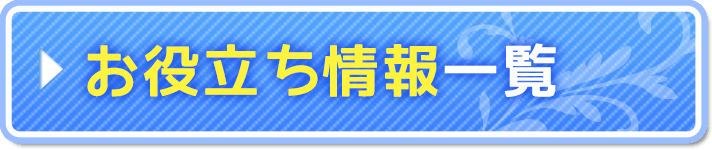相続税申告(相続発生後)
相続税についての税理士の選び方
1 相続税の計算結果は税理士によって大きく異なることがある

税金の計算というと、どの税理士が計算しても、それ程違わないのではないかという印象をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
現実には、相続税の計算結果は、税理士によって大きく異なることがあります。
これは、個々の財産の評価のルールについて、適用するかどうかが、納税者の判断に委ねられている部分が大きいためです。
このため、減額に繋がるような財産評価のルールを知らなければ、これを適用できず、高い評価額が算定されることとなります。
そして、税理士によって、このような財産評価のルールを知っているかどうかが異なるため、財産評価の結果も大きく異なってくることとなります。
不動産はもちろんのこと、投資信託等の金融資産であっても、税理士によって評価結果が異なり得ます。
この点を踏まえると、財産評価のルールを網羅的に把握している税理士を選ぶことができるかどうかが重要になってくることが分かります。
2 税理士をどのように選ぶべきか
それでは、このような税理士を選ぶためには、どのようにすれば良いのでしょうか?
重要なことは、税理士に財産に関する資料を示した上で、実際に相談してみることです。
その上で、税理士がどのような指摘、提案を行うかにより、税理士がどの程度財産評価のルールを知っているかについて、把握することができる可能性があります。
迷うときは、複数の税理士に相談してみても良いかもしれません。
税理士の指摘、提案内容を比較することにより、どの税理士が財産評価のルールに詳しいかを把握できることもあります。
実際に複数の相談をしてみると、税理士によって回答内容が大きく異なる部分があることも分かると思います。
ここで注意したいのは、複数の税理士の指摘、提案を比較し、最も税額が少ない回答を行った税理士に依頼するという方法は避けた方が良いと言うことです。
ある税理士から、税額が少ない回答を得たとしても、その税理士の知識や経験が不足しているため、不適切な回答がなされている可能性もあるためです。
このような回答に基づいて申告を行うと、後日、税務署から指摘がなされ、不足している本税だけでなく、本来納めなくても良かった加算税や延滞税を納めなければならなくなるおそれがあります。
税理士の回答を比較する際には、税額だけではなく、根拠付けも比較すべきでしょう。
相続税を払い過ぎるとどうなるのか
1 多くの場合は払い過ぎのままとなる

相続税については、申告納税制度が取られています。
申告納税制度とは、第一次的には、自分で税金の金額を計算して申告書を提出し、納付する制度のことを言います。
このように、第一次的には、自分で税金の金額を計算することとなっているため、計算間違い等により、相続税が払い過ぎになってしまっている可能性があります。
相続税を払い過ぎた場合は、どうなるのでしょうか?
基本的には、相続税が払い過ぎになっていたとしても、税務署から、そのことを指摘してもらえることはありません。
時々、税務署から、計算間違い等があるとの連絡があり、申告内容の減額修正が可能であることを教えてもらえることもありますが、多くの場合は、このようなことは教えてもらえず、払い過ぎのままとなってしまいます。
申告内容を減額修正したい場合は、基本的には、自分から一定の手続を取らなければならないこととされています。
2 更正の請求を行えば払い過ぎた分を返してもらえる可能性がある
申告内容の減額修正が可能である場合は、更正の請求を行うことにより、払い過ぎた相続税を返還してもらえる可能性があります。
具体的には、計算間違いにより、相続税額が過大になっていた場合は、更正の請求を行うことができます。
単純な計算ミスがこれに該当します。
財産の評価方法について、減額できる事情があったものの、この事情を考慮せずに評価してしまった場合は、減額できる事情を考慮することにより、相続税が減額される可能性があります。このような場合も、計算間違いに含められており、更正の請求ができることとなっています。
3 更正の請求の手続
更正の請求は、税務署に、更正の請求書を提出することにより行います。書式については、国税庁のホームページに掲載されています。
更正の請求書には、住所や氏名等の個人情報のほか、払い過ぎとなった相続税が還付となった場合の還付先の口座、還付されるべき金額等を記載します。
更正の請求を行う場合は、どのような計算方法で減額修正となったかを具体的に明らかにするため、修正分の申告書案も添付します。
更正の請求の内容について、税務署が妥当であると判断する場合には、更正の請求書に記載した口座に、払い過ぎた相続税が還付されることとなります。
還付の時期は、更正の請求書の提出から2か月のうちになされることが多いです。
他方、更正の請求の内容について、税務署が妥当ではないと判断する場合には、税務署から連絡がなされ、更正の請求書の内容について修正を求められることがあります。
更正の請求書を修正すると、修正後の内容に基づいて、相続税の還付がなされることとなります。
これに対し、税務署が更正の請求の内容を妥当ではないと判断した上で、むしろ、追加で納付がなされるべきであると判断した場合には、税務調査がなされることもあります。
4 更正の請求の期間に注意
更正の請求は、計算間違いを理由とする場合は、申告期限から5年間に行わなければならないこととされています。
申告期限は、基本的には、被相続人の死亡日から10か月後ですので、被相続人の死亡日からカウントすると5年10か月後が、計算間違いを理由とする更正の請求の期限になります。
申告期限から5年が経過してしまうと、更正の請求はできないこととなってしまいます。
相続税を申告・納付する義務者
1 相続税が課税される可能性がある人

⑴ 相続または遺贈により財産を取得した人
相続税は、相続または遺贈によって財産を取得した場合に課税される可能性があります。
まず、被相続人の法定相続人であり、遺産分割によって財産を取得した場合には、相続税の納税義務者になります。
また、遺産分割が未了であったとしても、申告期限が経過する時点(つまり、相続が発生したことを知ってから10か月後の時点)で、相続分を主張することができる場合には、相続税の納税義務者になります。
次に、遺言によって財産を取得することとなった場合も、相続税が課税されます。
法定相続人でなかったとしても、遺言によって財産を取得することとなった場合には、相続税の納税義務者になります。
他には、死因贈与によって財産を取得した場合も、相続税が課税されます。
死因贈与とは、被相続人が生前、誰かとの間で、被相続人が亡くなった場合に、財産を贈与することを合意することを言いますが、この場合も、遺贈と同じように扱われ、相続税が課税されます。
⑵ 生命保険金、死亡退職金を取得した人
相続または遺贈によって財産を取得した場合にはあたりませんが、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合も、相続税が課税される可能性があります。
この場合も、受取人が相続人であったとしても、相続人でなかったとしても、相続税が課税される可能性があります。
ただし、相続人が受け取った生命保険金と死亡退職金については、合計で500万円×法定相続人の金額までは、相続税が非課税となります。
このため、相続人が受け取った生命保険金、死亡退職金の合計額が、上記の金額を下回る場合には、相続税は課税されないこととなります。
他方、相続人ではない人が受け取った生命保険金と死亡退職金については、上記のような非課税枠はなく、全額について相続税が課税されることとなります。
⑶ 相続時精算課税制度により財産の贈与を受けた人
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与された財産については、2500万円までは、贈与税が課税されないこととなりますが、代わりに相続税が課税されることとなります。
このため、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた人についても、相続税の納税義務者になります。
2 課税価格が一定額を超えると、相続税の申告を行う義務が生じる
上記の人が相続税の申告を行う義務を負うのは、課税価格が基礎控除額を超える場合です。
課税価格は、おおむね、以下の計算式により算定されます。
相続財産の総額-相続債務の総額+生命保険金額・死亡退職金額+相続時精算課税制度により生前贈与された財産額+相続前3年以内(令和6年1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年に延長)に相続人等に対して生前贈与された財産額
つまり、上記⑴から⑶で受け取った財産の総額から、相続債務額を差し引く計算が行われることとなります。
また、相続または遺贈により財産を取得した人、生命保険金・死亡保険金を受け取った人が、相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を段階的に7年に延長)に生前贈与を受けた財産についても、相続税の課税価格に加算されます。
このようにして計算された金額が、基礎控除額を超える場合には、相続税が課税されることとなります。
そして、基礎控除額は、以下の計算式によって計算されます。
3000万円+600万円×法定相続人数
3 相続税の申告を行う義務はあるが、納付の義務を負わなくなる場合
相続税の課税価格が基礎控除額を超えている場合であっても、特例を利用することにより、相続税が課税されなくなることがあります。
具体的には、小規模宅地等の特例の制度や配偶者の税額軽減の制度を利用することにより、相続税が軽減されたり、非課税になったりすることがあります。
このような場合には、特例を利用する前提要件として、相続税の申告を行う義務はありますが、相続税の納付の義務を負わなくて済む可能性があることとなります。
なお、障害者控除や未成年者控除については、申告が要件となっていませんので、申告を行わなくても、これらの制度の適用を受けることができます。
もっとも、これらの制度を用いることができる場合であっても、税務署に対して、相続税の納付の義務を負わないことを明確にするため、扶養義務者にも特例を適用することを検討するためにも、相続税の申告を行った方が望ましいと言えます。
相続税を申告する際にかかる費用
1 税理士費用

相続税申告を税理士に依頼する場合、税理士費用が発生します。
相続税申告については、税理士に依頼せずに申告することも考えられるところではありますが、相続税は特に複雑な税目であり、本人で申告を行ったときの税務調査の確率も高いですので、税理士に申告を依頼することをおすすめします。
それでは、相続税申告を税理士に依頼する場合、どれくらいの費用が発生するのでしょうか。
税理士費用の定め方は、個々の税理士で異なりますが、ここでは、共通点を説明したいと思います。
まず、税理士費用は、相続税の課税対象となる財産額で決まります。
ここでいう財産額には、相続財産のほか、みなし相続財産となる死亡保険金や死亡退職金も含まれます。
この財産額が多ければ多い程、費用は高くなる可能性が高いです。
これは、財産額が多い程、個々に評価すべき財産の個数も増え、申告に要する労力が増えること、財産額が多い程、申告に伴って税理士が職務上負うリスクが高まることが理由です。
次に、財産の種類によって、費用が加算される場合があります。
不動産については、路線価等で個別に評価すべき場合には、費用が加算される可能性があります。
また、有価証券についても、非上場株式があり、複雑な評価を行うべき場合は、費用が加算される可能性があります。
これらの財産については、特に財産評価に要する労力が増える反面、労力をかけて工夫を行えば、合理的に評価額を減額することもできることがあるため、費用加算がなされる可能性があります。
他には、相続人や受遺者の人数によっても、費用が加算されることが多いです。
これは、相続人や受遺者の人数が増えると、生前贈与の有無を検討すべき対象が増えることとなりますし、申告にあたり、当事者間の意見調整をすべき場合も生じてくるためです。
2 その他の実費
上記以外に、資料収集や調査のための実費が必要になります。
大まかに分けて説明すると、以下のとおりです。
・ 親族関係
相続税申告を行うにあたっては、相続人が誰であるかを特定するため、戸籍を取得する必要があります。
市区町村役場で戸籍を取得する場合には、1通あたり450円または750円の費用が必要になります。
・ 不動産
登記情報、公図、地積測量図を法務局から取り寄せる際、費用が発生する可能性があります。
登記情報については1通あたり332円の、公図、地積測量図については1通あたり362円の費用が必要になります。
また、不動産の現地調査を行う場合の交通費が必要になることもあります。
・ 預貯金、有価証券
金融機関や証券会社で取引履歴や残高証明書を取得する場合に、金融機関や証券会社に対し、書類の発行手数料を支払う必要があります。
賃料と相続税
1 賃料が問題になる場合

被相続人が貸地や貸家を所有している場合には、賃料が定期的に被相続人へ支払われることとなります。
被相続人が貸地や貸家を所有していたとしても、すでに支払日が到来している賃料について、きちんと支払いがされている場合は、相続税申告の場面で賃料の扱いが問題になることは、ほとんどありません。
しかし、現実には、被相続人が亡くなった時点で、支払日が到来しているのに支払いがなされていない賃料があったり、逆に、支払日が到来していないのに、すでに支払いがなされている賃料があったりすることがあります。
このような場合に、どのように相続税の申告を行うかについては、注意が必要です。
2 相続税の考え方
相続税との関係では、被相続人が亡くなった時点で賃料の支払日が到来しているかどうかで、賃料が相続財産となるかどうかが変わってくることとなっています。
被相続人が亡くなった時点で賃料の支払日が到来していれば、賃料の全額が相続財産となり、相続税の課税対象にもなります。
他方、被相続人が亡くなった時点で賃料の支払日が到来していなければ、賃料の全額が相続財産にはならず、相続税の課税対象にもならないこととなります。
それでは、賃料の支払日は、どのような定め方をされているのでしょうか。
賃貸借契約書等を確認すると、おおむね、以下の2つのいずれかになっているものと思います。
① 当月分の賃料を当月の末日までに支払うものとする契約
② 当月分の賃料を前月の末日までに支払うものとする契約
ここで、被相続人が亡くなったのが6月3日だったと仮定します。
① 当月分の賃料を当月の末日までに支払うものとする契約の場合
5月分の賃料は、支払日が5月末日→すでに支払日が到来しているため、相続税の課税対象になる。
6月分の賃料は、支払日が6月末日→支払日が到来していないため、相続税の課税対象にならない。
② 当月分の賃料を前月の末日までに支払うものとする契約の場合
5月分の賃料は、支払日が4月末日→すでに支払日が到来しているため、相続税の課税対象になる。
6月分の賃料は、支払日が5月末日→すでに支払日が到来しているため、相続税の課税対象になる。
※6月分の賃料については、対応する賃貸期間は6月1日から6月30日ですので、6月4日から6月30日までについては、被相続人が亡くなった後の賃貸期間となります。
そうであったとしても、被相続人が亡くなる前に支払日が到来している以上は、6月分の賃料は、全額が相続税の課税対象となります。
このように、それぞれの賃料の支払日がいつになっているかを確認した上で、賃料が相続財産になるかどうかを確認する必要があるということとなります。
3 支払日が到来しているのに賃料の支払いがされていない場合
また、支払日がすでに到来しているのに、賃借人から賃料の支払いがなされていないことがあります。
いわゆる未払賃料です。
未払賃料については、支払日が到来している以上、賃料の全額が相続財産となり、相続税の課税対象になるものとされます。
このように、未収賃料が存在すると、実際には賃料を受け取っていないのにもかかわらず、その分、相続税が増額されることとなってしまいます。
未払賃料が年単位で発生している場合、相続税も大きく増額されることとなり、かなりの負担を余儀なくされることとなります。
以上から、相続税との関係では、未払賃料の問題は早期に解決されるべきであることが分かります。
4 支払日が到来する前に賃料が前払いされた場合
対して、支払日が到来する前に、自発的に賃料の前払いがなされることもあります。
いわゆる前受賃料です。
前払いされた賃料については、その支払日が到来する前に被相続人が亡くなると、賃料の全額が相続財産になりません。
そして、賃料の全額が相続財産にならない以上は、賃借人から返還を求めたら返還されるべきものと考えられますので、被相続人が負っていた債務となり、債務控除の対象とされます。
このように、前払いされた賃料は、被相続人に対して支払われており、被相続人の財産に組み込まれているにもかかわらず、債務控除により、相続税の課税対象から除外されることとなります。
前払いされた賃料の存在に気づくことができれば、その分、相続税が減額されることとなりますので、見逃さないようにしたいものです。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
1 配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは

配偶者が相続等によって取得した財産については、相続税が大きく軽減される可能性があります。
これは、相続税法において、配偶者の税額軽減(配偶者控除)の制度が設けられているためです。
相続財産については、配偶者の貢献によって形成されたものであるという側面がありますので、配偶者が相続財産等を取得することは、こうした貢献の精算の側面をもっています。
このため、通常の相続と同様に課税することは、不適切であるといえます。
また、配偶者の今後の生活保障のため、配偶者の税負担を軽減すべきであるという政策的理由もあります。
ただ、配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用を受けるにあたっては、いくつかの要件を満たす必要があります。
早期の段階で申告に向けての行動を開始しなければ、これらの要件を満たすことができなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
2 配偶者の税額軽減(配偶者控除)によりどれくらい相続税は減額されるのか
配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用を受けることができれば、配偶者が相続等によって取得した財産のうち、次の金額のどちらか多い金額までは、相続税が課税されないこととなります。
・ 1億6,000万円
・ 配偶者の法定相続分相当額
前提として、2つ目の配偶者の法定相続分相当額は、相続人が誰であるかにより、以下のとおり変わります。
① 亡くなった方の配偶者のみが法定相続人の場合
配偶者が100%
② 亡くなった方の配偶者と子や孫が法定相続人の場合
配偶者が2分の1
子や孫が2分の1
③ 亡くなった方の配偶者と父母が法定相続人の場合
配偶者が3分の2
父母が3分の1
④ 亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹や甥姪が法定相続人の場合
配偶者が4分の3
兄弟姉妹や甥姪が4分の1
例えば、亡くなった方の配偶者と子が法定相続人の場合、配偶者が取得した財産については、以下の金額までが非課税となります。
・ 遺産総額(債務控除後)が2億円の場合
1億6000万円>配偶者の法定相続分相当額2億円×2分の1=1億円
↓
配偶者については、1億6000万円までは非課税
・ 遺産総額(債務控除後)が4億円の場合
1億6000万円<配偶者の法定相続分相当額4億円×2分の1=2億円
↓
配偶者については、2億円までは非課税
このように、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を活用すれば、かなりの金額の財産が相続税の課税対象から外れることとなります。
3 相続放棄をした相続人がいる場合の配偶者の税額軽減(配偶者控除)
ところで、相続放棄をした相続人がいる場合、配偶者の法定相続分額はどうなるのでしょうか。
例えば、配偶者と子が法定相続人の場合、子が相続放棄をし、他に相続人がいないとすると、配偶者の法定相続分は100%となります。
このような場合には、相続財産の全額について、相続税が課税されないこととなるのでしょうか。
答えとしては、配偶者の税額軽減(配偶者控除)に関しては、相続放棄は考慮しないこととなっていますので、配偶者の法定相続分相当額は2分の1のままで計算されることとなります。
恣意的な相続放棄を行い、意図的に配偶者の税額軽減(配偶者控除)を増やすという相続税対策がなされることを防ぐため、配偶者の税額軽減(配偶者控除)の計算上は相続放棄を考慮しないこととなっています。
4 配偶者の税額軽減(配偶者控除)の要件
上にも書いたように、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、以下のとおりです。
① 被相続人の戸籍上の配偶者であること
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができるのは、被相続人の戸籍上の配偶者のみです。
いわゆる内縁関係にある人は、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができません。
戸籍上の配偶者でありさえすれば、別居状態であったとしても、婚姻後わずかな期間しか経過していなかったとしても、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができます。
② 遺産分割や遺言により、配偶者が取得した財産が(一部でも)確定していること
遺産分割や遺言により、配偶者が取得した財産が(一部でも)確定している必要があります。
遺産が未分割のままであれば、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができません。
配偶者以外の相続人が取得する財産が未分割であったとしても、配偶者が取得する財産が確定していれば、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができます。
一部の遺産を配偶者が取得するものとし、残りの遺産の分割方法については配偶者を含む相続人で追って協議するものとしていたとしても、 配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができます。
③ 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出すること
相続税の申告書を提出しなければ、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を受けることはできません。
申告期限までに相続税の申告を行っていなかったとしても、期限後に税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出すれば、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を受けることができます。
5 配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いる場合の手続き
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いる場合には、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出するとともに、一定の必要書類を提出する必要があります。
必要書類は、以下のとおりです。
① 戸籍謄本
被相続人と配偶者が婚姻関係にあることを証明するために必要です。
② 遺産分割協議書の写し、遺言書の写し
配偶者が取得した財産を明らかにするために必要です。
③ 印鑑証明書の原本(遺産分割協議書の写しを提出する場合)
真正に遺産分割協議が成立したことを証明するため、相続人全員の印鑑証明書の原本を提出する必要があります。
どうしても申告期限までに必要書類の準備が間に合わない場合は、申告期限後に必要書類を追完することで、特例の適用を受けることも可能ではあります。
生前贈与と相続税
1 被相続人から贈与された財産は相続税の課税対象になるのか

相続人から生前に贈与された財産について、相続税が課税されることがあります。
具体的には、相続などにより財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象になるとされています。
なお、令和6年1月1日以降から、この3年の期間が段階的に延長され、令和13年1月1日以降は相続開始前7年以内となります。
贈与された財産がすべて相続税の課税対象にならないとすると、被相続人が亡くなる直前に、相続税の課税対象を減らす目的で、駆け込みで贈与を行うという相続税対策がなされるおそれがあります。
このような駆け込みでの贈与による相続税対策を行えないようにするため、相続開始前の一定期間内の贈与も相続税の課税対象にするという規定が置かれているのです。
注意しなければならないのは、この贈与がいずれも、贈与税の基礎控除(受贈者1人あたり110万円)の範囲内であり贈与税の課税対象でなかったとしても、相続税の課税対象になるということです。
例えば、贈与された財産が10万円であったとしても、相続税の課税対象となります。
他方、相続税の課税対象となる贈与について贈与税が課税されていた場合は、贈与税の額を相続税の額から引き算することとなっています。
贈与税と相続税が二重に課税されることを防ぐため、このような調整が行われています。
2 誰に対してなされた贈与が相続税の課税対象になるのか
相続税の課税対象になる贈与は、相続などにより財産を取得した人が受けた贈与です。
裏を返せば、相続などにより財産を取得しなかった人が受けた贈与は、相続税の課税対象にはなりません。
したがって、相続人であっても相続人でなくても、相続などによって財産を取得した人については、相続開始前の一定期間内の贈与にも相続税が課税されますが、財産を取得しなかった人については、生前の贈与に相続税が課税されることはないということになります。
なお、相続などにより財産を取得した人には、相続財産を取得した人だけでなく、生命保険金や死亡退職金を取得した人も含まれますので、注意が必要です。
例えば、被相続人の孫(代襲相続人ではない)が生命保険金を受け取っている場合は、相続開始前の一定期間内の贈与にも相続税が課税されます。
3 贈与税が課税されない特例の適用を受けている場合
贈与税については、特例の適用を受けることにより、贈与税が課税されないこととなることがあります。
例えば、結婚して20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与財産のうち2,000万円までの部分については、贈与税が非課税となります。
このように、特例を適用して贈与税が課税されないこととなっている場合には、相続開始前の一定期間内になされた贈与であっても、相続税の課税対象にはならないものとされています。
特例を適用して贈与税が非課税となっている以上、相続税も非課税とされるべきと考えられるからです。
このように、贈与税が課税されない特例の適用を受けた結果、相続税の課税対象にもならないとされるものとしては、以下のものがあります。
・ 贈与税の配偶者控除(先述)
・ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与のうち、非課税部分
・ 直系尊属からの教育資金の一括贈与のうち、非課税部分
・ 直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与のうち、非課税部分