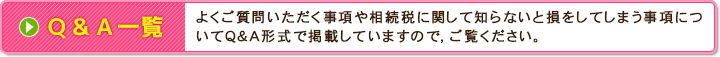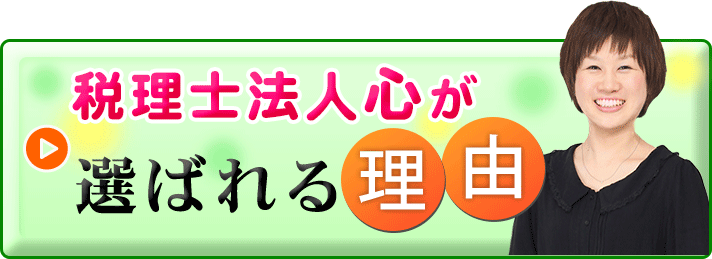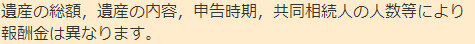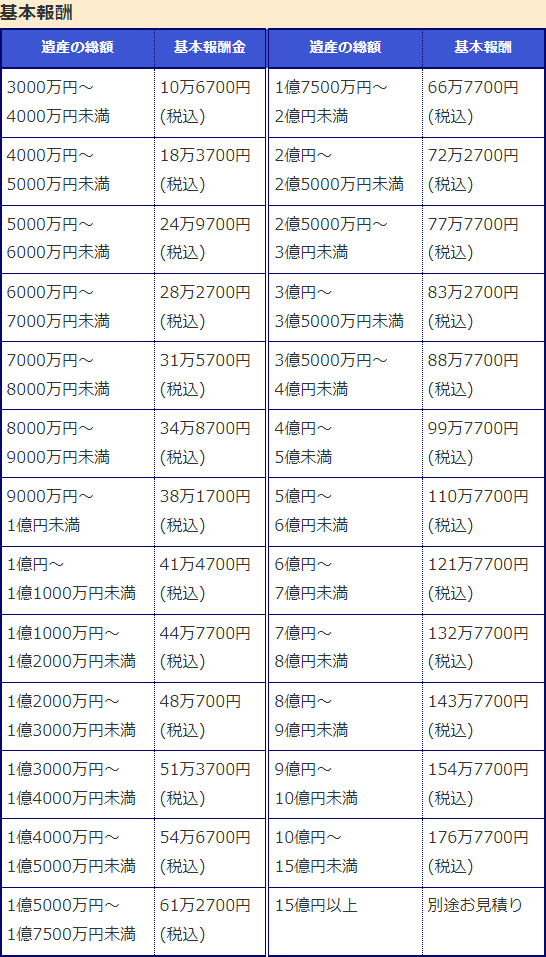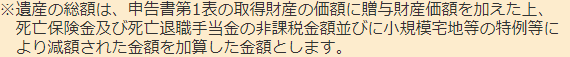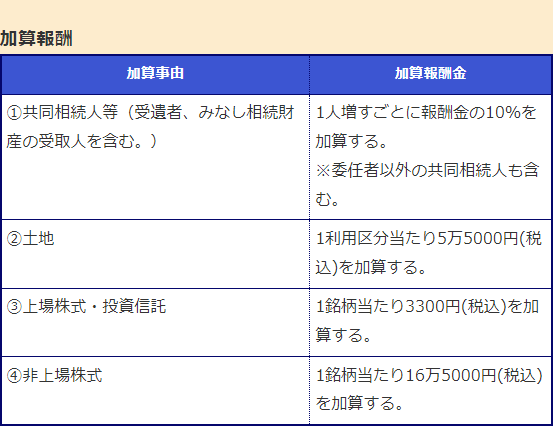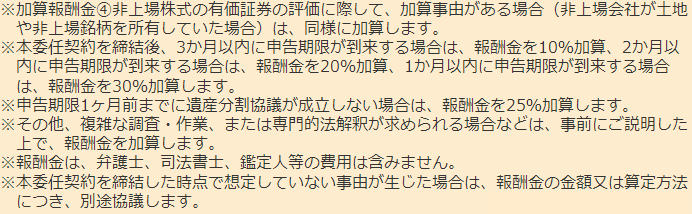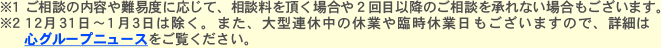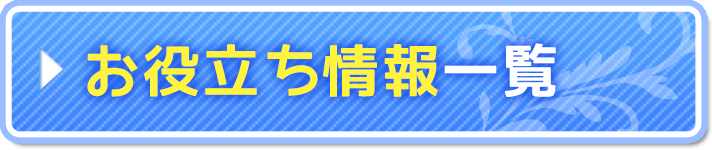「相続税対策」に関するお役立ち情報
生前贈与で失敗した事例
1 事例の概要
この事例では、ご本人は、多額の預貯金を有しており、多額の相続税が課税されることが予想されたため、相続税対策として、生前贈与を行うことを希望していました。
保険会社の人は、上記の話を聞いて、ご本人に対し、以下のような保険を組むことを提案しました。
- ➀ 保険の契約者を孫、被保険者をご本人、受取人を孫として、生命保険契約を締結する。
- ② 毎年の保険料については、100万円に設定する。
- ③ 保険料については、被相続人の口座からの引落とし、被相続人から孫に対し、保険料の贈与があったものと扱う。
上記のようにすれば、毎年の保険料の引落により、ご本人から孫への保険料の贈与が自動的になされることとなります。わざわざ、ご本人から孫に対して現金を交付する必要もなく、贈与の手間も省けることとなります。
そして、贈与の額は、毎年100万円であり、贈与税の基礎控除額である毎年110万円を下回る金額ですので、贈与税が課税されることはありません。
しかも、ご本人の子であり、孫の親である人物は存命でした。このため、ご本人が亡くなったとしても、孫は法定相続人には該当しないこととなります。法定相続人に対する贈与は、ご本人が亡くなった日から7年間遡り、相続税の課税対象とされてしまいますが、今回は、法定相続人ではない孫に対する贈与ですので、相続税の対象とされることもありません。
このように説明すると、良いとこ尽くしの相続税対策であるように思います。
ご本人も、このような説明に納得し、保険契約を組むこととなりました。
2 この相続税対策の問題点
その後、ご本人が亡くなり、相続税申告を行うこととなりました。
しかし、相続税申告にあたり、申告書作成を依頼した税理士から、上記の保険については、いわゆる名義保険と扱われ、被相続人が契約していた保険と同様に扱われることとなるため、相続税の課税対象になってしまうとの説明がなされました。
しかも、税理士によると、保険金の受取人が法定相続人ではないため、500万円×法定相続人の非課税枠を利用することもできず、さらに、相続税が2割加算されることとなると言うのです。
このように、申告時の税理士の説明は、当初の想定とは180度異なるものでした。
一体、この相続税対策のどこに問題点があったのでしょうか?
国税庁は、昭和58年9月に、以下の事務連絡を行い、被相続人が保険料を負担した保険契約については、相続税の課税対象になるとの考え方を示しました。
被相続人が保険料を負担していたことについては、被相続人からの贈与関係が生じないとして、被相続人が亡くなったことにより、保険金を受け取った子や孫(今回の事例だと孫)に対して、相続税を課税することとなるというのです。
これは、いわゆる名義保険という考え方であり、被相続人が保険料を負担していた保険については、被相続人が契約していた保険と同様、相続税の課税対象となってしまうこととなります。
ただ、事務連絡は、以下の事実関係がある場合には、保険料の贈与があったとして、契約者である子や孫(今回の事例だと孫)の保険であるとの主張を認めるものとしています。
- ➀ 毎年、保険料の贈与について、贈与契約書を作成していること
- ② 保険料の贈与について、贈与税の申告を行っていること
- ③ 子や孫の確定申告において、子や孫の保険契約についての保険料であるとして、生命保険料控除の利用がなされていること
- ④ その他贈与の事実が認定できるもの
今回の事例では、贈与の手間が省けるとの売り文句につられて、贈与契約書の作成はなされておらず、年110万円を下回る贈与であったため、贈与税の申告もなされていませんでした。
孫は確定申告を行っておらず、生命保険料控除も利用していませんでした。
このため、上記➀から④の基準にあてはめると、保険料の贈与がなされたものと扱うことはできず、名義保険の認定がなされ、被相続人が契約していた保険契約と同様に相続税の課税対象と扱われるリスクが大きい案件でした。
保険料の贈与があったものと扱ってもらうためにも、上記➀から④の手を打っておく必要があった案件であると言えました。
このように、十分な知識のないまま相続税対策を行うと、結果的に、相続税対策が功を奏しないばかりか、むしろ、税額が増加してしまうような事態を招きかねません。
相続税の生前対策を行うのであれば、税理士から適切な助言を得た上で、実行に移すのが望ましいと言えます。