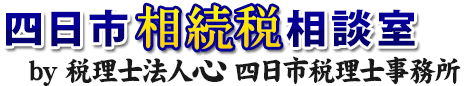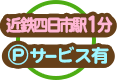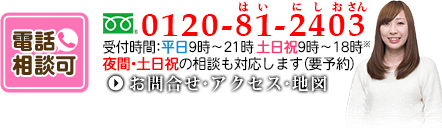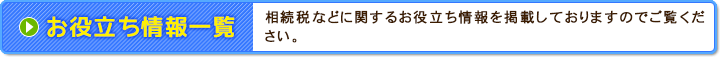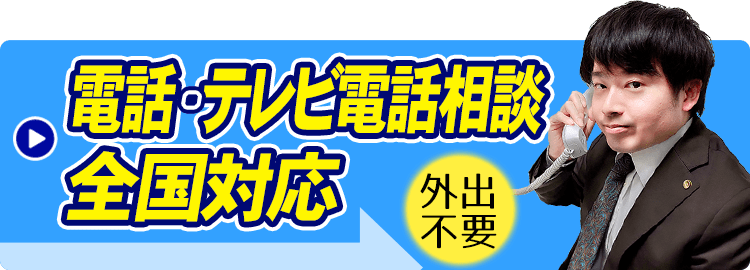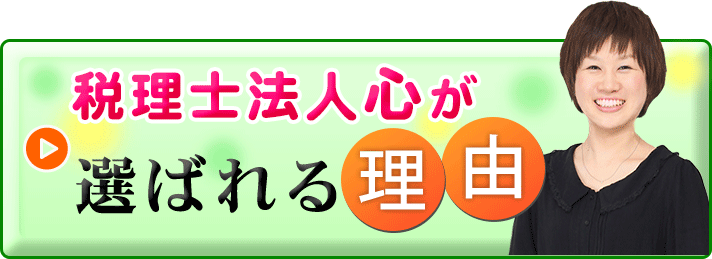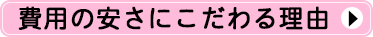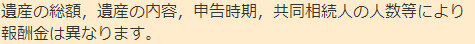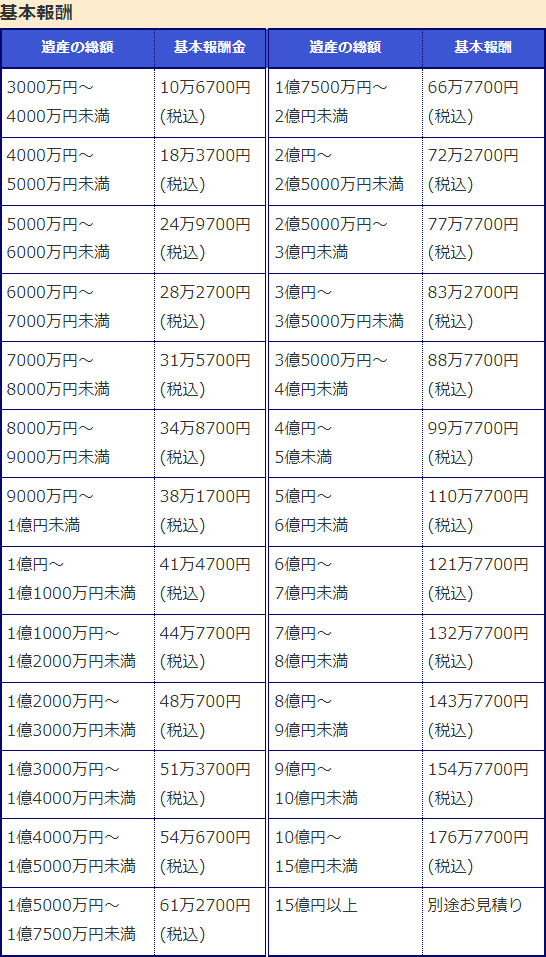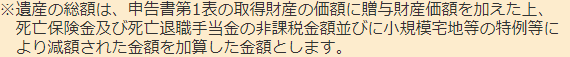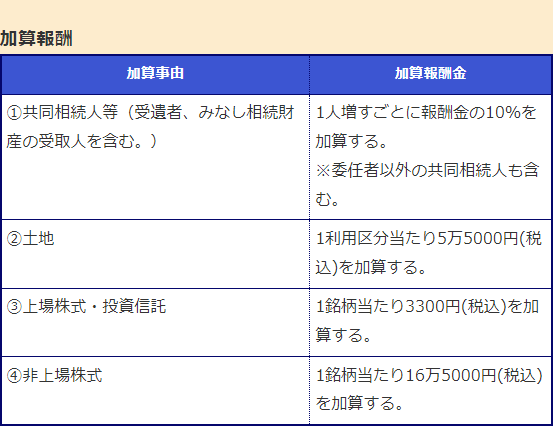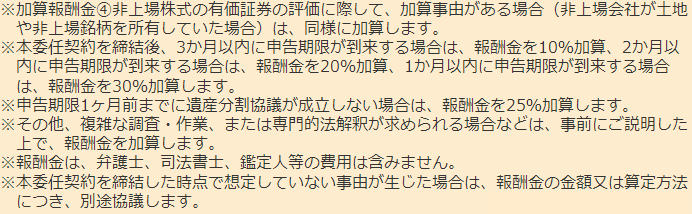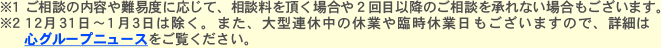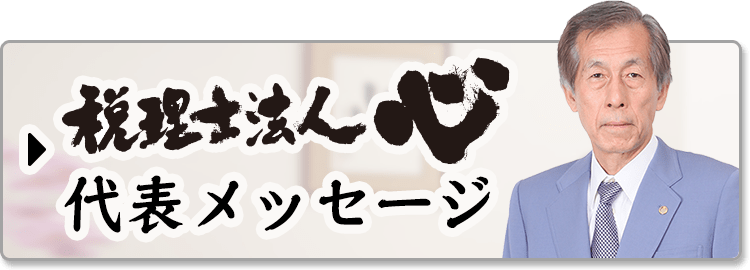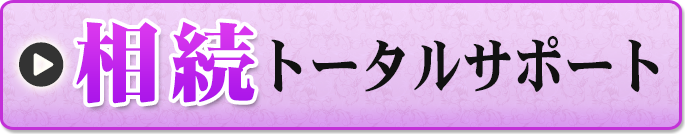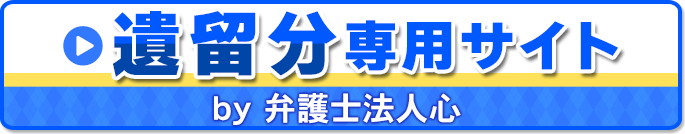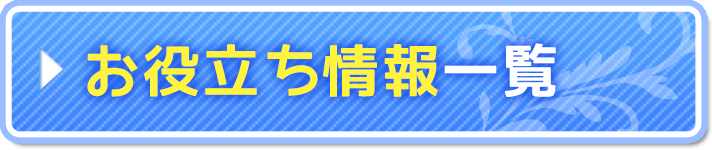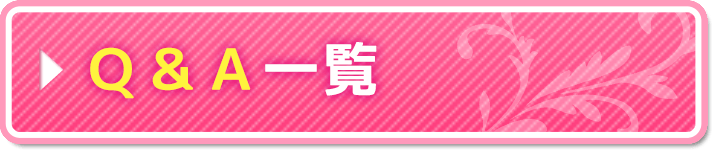相続税の申告期限に間に合わないときのQ&A
相続税の申告期限に間に合わないと、どうなるのでしょうか?
相続税の申告期限に間に合わない場合は、本来納付すべき相続税(本税)に加えて、無申告加算税や延滞税を納付しなければならなくなります。
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対して課される税金であり、延滞税は、期限内に納付しなかったことに対して課税される税金です。
無申告加算税はどのくらい課されるのでしょうか?
申告期限に間に合わなかった時点で、少なくとも、本税の5%の無申告加算税が課税されます。
ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告を行い、かつ期限内に申告する意思があったと認められる場合には、無申告加算税が免除されることがあります。
税務調査の事前通知がなされた場合には、無申告加算税は、50万円までは本税の10%、50万円を超えて300万円以下の部分は本税の15%、300万円を超える部分は本税の25%となります。
また、税務調査がなされた場合には、無申告加算税は、50万円までは本税の15%、50万円を超えて300万円以下の部分は本税の20%、300万円を超える部分は本税の30%となります。
なお、無申告加算税の額が5000円未満であるときは、無申告加算税は切り捨てにより課税されないこととなります。
延滞税はどれくらい課されるのでしょうか?
延滞税の税率は、時期によって異なります。
これは、延滞税の税率が、銀行の新規の短期貸出約定平均金利利率によって変動することとなっているからです。
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間については、延滞税の税率は、納期限から2か月後までについては年利2.4%、2か月が過ぎた以降については年利8.7%とされています。
ここでいう納期限とは、申告期限を過ぎてから申告することとなってしまった場合は、期限後申告を行った時点のことをいいます。
つまり、令和5年の申告において、当初の10か月の申告期限が経過し、さらに6か月が経過してから期限後申告を行った場合には、申告期限から8か月が経過するまでは年利2.4%の税率となり、その後は8.7%の税率となります。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
相続税の申告期限までに申告の準備が間に合わない場合は、どうすればよいのでしょうか?
⑴ いったん概算の税額で申告・納付
これまでみてきたとおり、申告期限までに申告を行うことができなければ無申告加算税が、申告期限までに納付を行うことができなければ延滞税が追加で課税されることとなります。
では、申告期限までに準備が間に合わないときに、無申告加算税や延滞税の課税を避けるためには、どうすればよいのでしょうか。
結論としては、概算でも構わないため申告書を作成・提出し、納付を行うべきであると思います。
例えば、土地については固定資産評価額の1.2倍〜1.3倍、建物については固定資産評価額、有価証券については証券会社作成の取引残高報告書の資産合計額、預金は相続時点の残高の合計額といった形で、概算で評価額を算定すれば、短時間で概算の申告書を作成することができます。
納付についても、いったん概算額で行います。
⑵ その後の対応方法
もっとも、概算の申告書は正確性には欠けているでしょうから、そのままで終わりにしてしまうと、調査選定等の対象になってしまう可能性があります。
このため、後日、きちんと財産調査や財産評価を行った上で、正式な申告書を作成し、提出する必要があります。
正式な申告書で、当初の概算よりも税額が増加したときは、不足額を追加で納付します。
正式な申告書で税額が減少したときは、差額について更正の請求をし、還付を受けます。
このような方法を用いれば、無申告加算税の発生は避けることができます。
また、当初の申告書の金額が過少であった場合には、過少申告加算税の対象になる可能性がありますが、早期に自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は課されません。
加えて、この場合の不足額には延滞税も発生しますが、あくまでも差額に対する延滞税ですので、限られた金額に抑えることができると思われます。
このため、いったん概算で申告書を提出・相続税を納付してから、きちんと財産調査や財産評価を行った上で、正式な申告書を早期に提出すれば、ペナルティを0または最小限に抑えることができる可能性があります。
相続税と贈与税の違いに関するQ&A 相続税の書面添付制度に関するQ&A